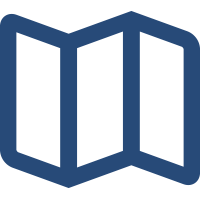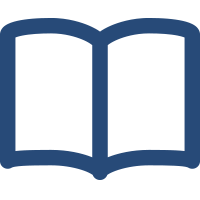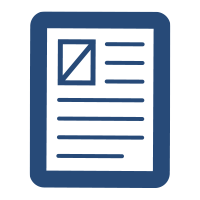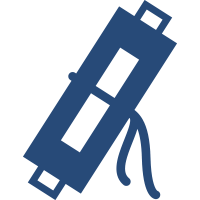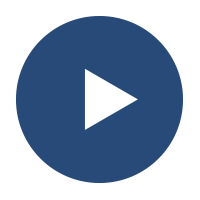中小企業の経営者からDXに関するご相談をいただく際、その冒頭で必ずと言っていいほど出てくる言葉があります。「うちはITに詳しい人材がいないから進まない」「現場が新しいことを覚えるのを嫌がって抵抗する」――。 確かに、人材不足や現場のリテラシー課題は存在します。しかし、多くの企業の支援現場に立ち会ってきた立場から申し上げますと、DXが停滞・頓挫する本当の原因は、そこではありません。DXが進まない最大のボトルネック、それは「経営判断そのものの欠如」にあるケースが大半です。
本稿では、なぜ多くの中小企業でDXが「ツール導入」で止まってしまうのか、その真因と、経営者が果たすべき本来の役割について解説します。
■「どうせなら最初から全部つなげたい」という判断の罠
DXに取り組もうとする際、経営者やプロジェクトリーダーからよく聞かれるのが、「業務を効率化したい」「データを一元化したい」という要望です。そして、その解決策として頻出するのが、「どうせやるなら、最初から全部つなげた方がいい」という判断です。 販売、在庫、会計、顧客情報。これらがバラバラだと非効率だから、最初からすべてのデータがシームレスにつながり、リアルタイムで数字が見える状態にしたい。将来を見据えたこの発想自体は、一見すると合理的であり、正論に聞こえます。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。 多くの失敗事例において、この「全部つなげたい」という発想は、将来のあるべき姿(To-Beモデル)から逆算されたものではなく、単に「今の不便さを一気に解消したい」という現状(As-Is)起点の発想になってしまっているのです。
■「今の業務」をそのままデジタル化してはいけない
現状起点でシステムを一気に連携させようとすると、何が起きるでしょうか。 中小企業の現場業務は、長年の間に担当者ごとの属人的な工夫や、取引先ごとの例外処理(「A社だけはFAXで注文書が来る」「B社だけは締め日が違う」など)が複雑に絡み合っています。これらは、現場が日々努力して回している「現実(As-Is)」です。
しかし、DXの目的は、この複雑な現状をそのままデジタルの上に載せ替えることではありません。もし、業務プロセスを整理しないまま「全部つなぐ」ことを目指せば、システム側で膨大なカスタマイズが必要になるか、あるいは現場がシステムに合わせて無理な運用を強いられることになります。 「システムを入れたら、かえって入力項目が増えた」「前のやり方の方が早かった」という現場の不満は、業務の整理(断捨離)をせずに、今の混沌とした業務フローをそのままIT化しようとした結果として生まれます。これは「ITツールの良し悪し」ではなく、「業務設計の放棄」という経営の失策です。
■To-Beを『仮説』として描くスモールスタートという考え方
ここで必要になるのが、「To-Beモデル(あるべき姿)」の策定です。 To-Beモデルとは、単なるシステムの完成図ではありません。「そもそも、我が社は将来どのような組織でありたいのか」「顧客にどのような価値を提供するために、業務はどうあるべきか」という経営としての理想像です。
例えば、「これまでは顧客ごとの例外対応を強みとしてきたが、人手不足の今後は、標準化されたサービスをスピーディーに提供する体制へシフトする」というTo-Beを描いたとします。そうであれば、システム導入の要件は「例外対応のしやすさ」ではなく「標準機能での処理スピード」が優先されるはずです。 逆に、このTo-Beが描けていないと、経営者は何を基準に判断(意思決定)すればよいのか分からなくなります。
「現場は使いにくいと言っているが、導入すべきか?」
「A社のツールとB社のツール、どちらがいいか?」
「どこまでコストをかけるべきか?」
これらの問いに対する正解は、ツールのカタログスペックの中にはありません。自社のTo-Beモデルという「設計図」の中にしかないのです。その前提がないまま進めると、経営判断は現場の「楽をしたい」という声や、ITベンダーの「最新機能」という提案に右往左往することになります。結果として社内調整が長期化し、DXは「進まない」のではなく、組織が疲弊して「止まってしまう」のです。
■中小企業のDXは、To-Beを「仮説」として小さく描く
とはいえ、不確実性の高い現代において、最初から完璧なTo-Beモデルを描くことは大企業でも困難です。「将来のことが分からないから決められない」と足踏みをしていては本末転倒です。 そこで、中小企業にとって現実的な解となるのが、To-Beを「仮説」として描き、小さく試す(スモールスタート)というアプローチです。
最初から全体最適を目指した壮大な計画を立てるのではなく、まずは「在庫管理だけ」「勤怠管理だけ」といった、単体でも効果が出やすく、業務が独立している領域から着手します。 この段階では、他業務との連携は、あえて「人手によるCSVデータの受け渡し」や「Excel集計」を残しても構いません。最初から完全自動連携を目指すと、データ形式のすり合わせだけで数ヶ月を要してしまいますが、手動連携であれば今日からでも始められます。
重要なのは、「すべてが自動化されていること」ではなく、業務が止まらずに回り、現場が「数字がすぐに見えるようになった」「残業が減った」という変化を実感できているかどうかです。この小さな成功体験(クイック・ウィン)こそが、次のステップへ進むための推進力となります。
■「つなげない」という選択も、立派な経営判断
小さな取り組みを通じて業務が整理され、データが蓄積されてくると、「次は販売と在庫をつなげよう」「ここはまだ手動でいい」といった判断が、より解像度の高い状態で行えるようになります。 このとき初めて、全体最適に向けたシステム統合の議論が意味を持ちます。すべてを一度に決める必要はありません。成果と課題を見ながら、判断を一つずつ積み重ねていく方が、結果として手戻りのない、確実なDXにつながります。
「最初から全部つなげない」という選択は、決して消極策ではありません。To-Beを仮説として描き、検証しながら前に進むための、極めて合理的かつ戦略的な経営判断なのです。
■DXは「仕組みづくり」ではなく「決断の積み重ね」
DXの本質は、ITツールを導入することではありません。自社は将来どのような業務・組織でありたいのか。そのために、今は何を捨て、何を変えるのか。 その“あるべき姿”をどのように描き、どこまでを今決め、どこを後に回すのか。その「判断の積み重ね」こそが、DXの成否を分けます。
もし今、貴社でDXが進まないと感じているのであれば、ツールの機能比較や現場への説得を一度止めてみてください。そして、経営者ご自身が「自社のTo-Be(あるべき姿)」を言葉にできているか、そして「やらないこと」を決める判断を先送りにしていないか、振り返ってみてはいかがでしょうか。 ITの専門知識は外部の専門家に任せることができます。しかし、「会社をどうしたいか」という意志決定だけは、経営者にしかできません。その決断こそが、DXを再び前に進めるための最初の一歩になるはずです。
小島 慶亮(こじま けいすけ)
中小企業診断士
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会 中央支部 副支部長/執行委員
経営戦略と現場業務の両面から企業の成長を支援するコンサルタント。 近年は生成AI活用やDX推進の支援に注力。ツール導入ありきではなく、「何のために導入するのか」という目的の言語化や、業務の棚卸から伴走し、経営判断の軸を作る支援を行っている。 講師としても、DX人材育成や生成AI活用ワークショップ、ノーコード実践などの研修を企画・登壇。デザイン思考やロジカルシンキングを組み合わせた、「自ら考えて変革できる人材」の育成に定評がある。